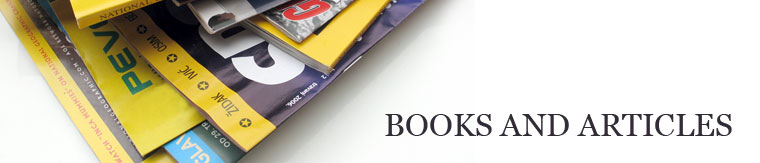アメリカ人ビジネスマンとのコミュニケーション術
「外国語ができる」よりも大切なこと
今日ではアメリカ企業と取引をしたり、M&Aによりアメリカ企業が親会社または子会社である会社はたくさんあり、日常的にアメリカ人とビジネスコミュニケーションをしている日本人の数は多くなりました。また、親の仕事の都合で子供のころアメリカに住んでいた経験があったり、学生時代に長期留学したりと、アメリカ社会を深く知る人も少なくありません。とはいえ、アメリカ人と自由に、しかも上手にコミュニケーションを図れる日本人が全体的に増えているかというと、そうではないようです。
多くの日本人は、外国人と上手にコミュニケーションができない理由を「言葉の違い」にのみ帰してしまいがちです。しかし、たとえ外国語がネイティブなみに話せたとしても、コミュニケーションがうまくういくとはかぎりません。
じつはコミュニケーションがうまくいくかどうかは、相手が外国人であるか日本人であるかはあまり関係ありません。コミュニケーションで何よりも大切なのは、相手をよく理解すること、言葉だけでなく、習慣の
違い、嗜好の違い、つまり価値観の違いを理解することだからです。
相手の気持ちを察する事ができれば、コミュニケーションはうまくいく。この原則に言語の違いは関係ないのです。
「朝令暮改」がアメリカ人のスタイル
アメリカ人とのコミュニケーションがうまくいかない原因を、「わがまま」「自己中心的」といった、アメリカ人の性格のせいにする日本人の方がいます。たしかに日本人と比べれば、アメリカ人には結果を急ぐ傾向があり、我慢強さにかける面もありますが、その理由を知っておくことが大切です。
たとえば、アメリカ企業とビジネスをしている日本人からよく聞くのが、「アメリカ人は言うことがころころ変わる」という愚痴です。
「前回の打ち合わせではこれがいいと言ったのに、今回はあっちがいいと言われた」といったことが頻繁に起こるためです。
契約社会のアメリカでは、双方が合意して契約書をとりかわすまで、ベストの答えを探し続けます。「ビジネスはつねに変化しつづける生き物であり、それに対応しなければ企業は競争に生き残っていけない。刻々に変化する状況にあわせて判断していくのだから、その時々でいうことがことなるのも当然だ」というのがアメリカ人の考えです。つまり朝令暮改こそがアメリカ人ビジネスマンの思考スタイルなのです。
このように相手の事情を知ることにより、日本人にとって一見ネガティブなアメリカ人の性格にもそれなりの理由があることがわかります。そういった言動の背後にあるものの考え方を知ることによって、相手と和やかに会話することができるようになり、良い関係が継続され、結果としてお互い納得のいく交渉ができることになるのです。
曖昧な表現は誤解を生む
一般的に言ってアメリカ人は交渉がとても上手です。一方、日本人は交渉ベタ、とされています。交渉ベタな日本人が、アメリカ人と交渉に臨む場合には、どのような点に注意すべきでしょうか?
まずは、考えられる争点を列挙して、それぞれについて先方の出方を想定し、こちらの反論を準備しておくことです。その際、直接英語で交渉するにせよ、通訳を介すにせよ、どのような言葉を用いてこちらの考えを伝えるか、単語レベルで検討することを怠ってはいけません。これを怠ると、伝えたい内容が相手に届かなかったり、こちらの思想とはことなるニュアンスで解釈されてしまったりして、交渉の不調を招いてしまうリスクがあります。
とくに注意しなかればならないのが日本人独特の曖昧な表現です。たとえば、ある事をやるかどうかが問われている場面で、肯定の意味で「一生懸命がんばります」という表現を用いても、アメリカ人にはどちらなのかわかりません。「がんばるかどうか」ではなく、「やるかどうか」をもっと端的に答えてくれ、というわけです。まわりくどいだけならまだしも、相手にとって都合のよい解釈をされてしまう恐れもあるので、このような曖昧な表現はアメリカ人との交渉では避けなければなりません。
担当者には決定権をもたせる
担当者同士で話し合いを行い、ある程度の地ならしをしてから次第に権限の大きな上司との交渉に移っていく日本的なやり方はアメリカにはありません。交渉の重要性に応じて、最初からそれにふさわしい役職の人が交渉にあたります。その点に留意して、交渉担当者を選ぶ際には、決定権をもった役職者にするか、あるいは、担当者に決定権を付与すべきです。
よく日本企業にある悪い事例が、英語ができるという理由だけで交渉者を選んでいるケースです。そのような担当者の場合、英語でのやりとりはできても、その場での意思決定は保留し、上司の判断を仰ぐため社に持ち帰らなければならないことになってしまいます。これでは、ネゴシエーター(交渉者)というよりも、メッセンジャー(伝言者)です。
合理主義のアメリカ人にとって、これほど効率のわるい、苛立たしいことはありません。本気で交渉する気がないのではないかと疑われる場合さえあります。いずれにしても、交渉上得策ではありません。
キーワードは「パートナー」
アメリカ人は「パートナー」という言葉をよく使います。ビジネスでも、共同経営者についてはもちろんのこと、従業員や取引先に対してさえパートナーと呼ぶことがあります。そこには「相手と組む」という意味合いに加え、「同等な関係」というニュアンスが強く含まれています。
この言葉の背後には、「自らのビジネスの関係者全員がベネフィットを得るべき(これをwin-win gameといいます)」との考え方があります。つまり、売る側も、買う側も、立場は違うものの、取引を通じてお金もうけをしようとする点において目的を同じくするパートナーだというわけです。
日本人は自分が売る側だったり、自社よりも規模の大きな企業と交渉をする場合、卑屈とも思える態度をとりがちです。日本国内では、あるいはそれは自然な態度なのかもしれません。しかし、アメリカ人に対しては、そのような態度はむしろ不信感を招きます。
人間関係が崩れてしまうのではないかと恐れるあまり、ハードな交渉を避けようとする日本人の特性も同様です。アメリカ人にとっては、双方が利益を得ることを目的としている以上、交渉の過程でまずはお互いが自己の利益を主張するのは当たり前だと考えます。そして、激しく議論を交わすなかで、落としどころを探っていくわけです。日本人も、お互いがよりよい結果を目指しているのだという姿勢を示すためにも、堂々とした態度で交渉に臨む必要があるでしょう。
念のために言い添えておくと、傲慢な態度をとれと勧めているわけではけっしてありません。いうまでもなくそれは逆効果です。アメリカ人が日本人を「礼儀正しくまじめ」だと、他のどの国のビジネスパーソンよりも高い評価をしていることも忘れてはならないでしょう。
アメリカ人ビジネスマンとのコミュニケーション術記事全体をダウンロードする